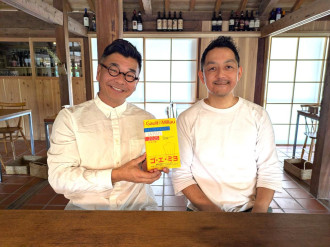「石垣島の水環境を考えるシンポジウム」が2月11日、石垣市健康福祉センター(石垣市登野城)で行われた。
同シンポジウムで、法政大学文学部地理学科の水文(すいもん)地理学教室の小寺浩二准教授が、「石垣島の海・山・川と人々の暮らし-水環境の現状と今後の保全のために-」と題して講演。続くパネルディスカッションでは、地元石垣島で環境保護活動を行っている「アンパルの自然を守る会」から谷崎さん、於茂登岳近くの集落に長年住む嶺井さんなどが参加し、会場からの発言も交えて石垣島の環境問題について話した。
これまで小寺さんが取り組んできた吉野川河口堰問題や島原半島トンネル問題などの実例を挙げ、自然環境の保全の問題解決には、学民の継続的なシンポジウムの開催や産官学民が一緒に取り組むことが大切と訴えた。旧ソ連のアラル海問題を挙げ、人が自然環境に及ぼす影響が多大であることに警鐘も鳴らした。
公共水域調査の公表されている結果から、石垣島の宮良川と名蔵川で1998年と1999年にBOD値の異常上昇があったことも挙げ、石垣島でこの時何があったのかとの問い掛けたほか、身近な水環境一斉調査への参加を呼び掛け、シンポジウムの開催継続などを要望した。
シンポジウムに参加した30代男性は「データやマクロな視点も必要だと思うが、今度はもっと石垣島に特化した内容のことを聞きたい」と話す。
小寺さんは「10年くらい前から数年間石垣島で調査をやってきていたが、今回、いろいろ河川の水質調査をして、やっぱり石垣島の水質は不思議なことが多く面白い。今後は継続した調査を行いたい」と話す。